先輩の声
認知症看護認定看護師
認知症についての理解は社会的にも深まりつつありますが、認知症患者さんやそのご家族の苦労は計り知れないものがあります。また、医療現場のスタッフもどのように関わるべきか日々悩んでいます。
私は認知症看護認定看護師として、認知症患者さんの失われた機能を明確にし、残された機能を探しだし、患者さんの人生を辿りながら大切にしてきたものを見つけることに取り組みます。
そして、認知症患者さんがここに居ても良いと思えるような心地の良い環境をスタッフと共に調整し、治療やケアがスムーズに受けられることを目指します。認知症患者さんの権利を擁護し、ご自身の意思が表出できるように環境を整え、介護家族の方への支援もしていきます。

荒木佳子
緩和ケア認定看護師
緩和ケアとは、病による患者さんとご家族の苦しみを和らげ、QOLの改善を図ることを目的としています。疾患や病期、そして提供の場所を問わず、切れ目なく実践することが求められています。しかし、それを実現するためには様々な課題があるのが実情です。
聖母病院では、日本に緩和ケアという言葉が定着するずっと以前から、地域の方々の「誕生から最期を迎える時までの健やかな生活」を支えることに尽力してきました。現在は緩和ケアチームの活動を通して、特にがん患者さんの治療と療養の両立、終末期あるいは高齢患者さんのエンド・オブ・ライフ・ケアに、多職種連携を基盤として専門的に取り組んでいます。そして院内だけではなく、在宅医療の現場との連携強化も図りながら、地域全体の緩和ケアの推進を目指しています。

三浦恵美子
摂食・嚥下障害看護認定看護師
人が「口から食べる」ということは、生命維持のためだけでなく、日常生活の楽しみの1つである生理的・精神的・社会的側面から喜びを得るものであり、脳を刺激し活性化させるものです。その為、何気なく行っている食事という行為は、多くの意味を持ちます。
しかし、疾患あるいは加齢に伴う生理的機能変化から、摂食・嚥下機能が低下し口から食べるという事が難しくなります。そのような患者さんの「口から食べたい」という思いに寄り添い、口から食べることが続けられるように支えていくことは大切です。
多職種と連携し、摂食・嚥下障害の原因や支援方法についてアセスメントし、安全で適切な口腔ケア方法・食事内容・食事摂取方法を判断し、誤嚥性肺炎、窒息、低栄養、脱水などの予防や改善を行います。一人でも多くの患者さんが、患者さんのQOLに大きく関わる「口から食べる」ことを少しでも長く、安全に続けられるように支援していきます。

松崎佐希子
これまでの経験が活かせる病棟
私が勤務している地域包括ケア病棟とは、急性期治療を経過し病状が安定した患者様に対して、住み慣れた地域での療養(在宅や一部の介護施設への復帰)を支援する病棟です。
入職時は、以前勤めたリハビリ病院で培った退院支援の経験を活かしてみたいと思い、聖母病院の地域包括ケア病棟に就職しました。
この病棟には、退院支援を必要とする方々はもちろんのこと、急性期に近い治療を要する方の入院も意外に多く、他にも当院でのお看取りを希望される方など、地域に根差した病院だからこそ、様々な病状の方々が入院されます。
そのため、私がここにいたるまでの急性期病棟やホスピスでの職務経験も、無駄になることなくすべて活かすことができますので、どの様な症状の方にもやりがいを持って看護することができます。

看護師 E・A
忙しい日々の中でも、あたたかな看護を
私が働く一般急性期混合病棟は、その名の通り、複数の診療科を有する混合病棟で、さまざまな疾患に対応しております。
そのため、看護師がこれまでに培ってきた知識や看護技術を遺憾なく発揮することができる環境です。
他院で職歴のあるスタッフも多く在籍し、多様な経験を持つ仲間とともに、日々の看護に取り組んでいます。
入院して来られる患者様の多くは、近隣地域の方々のため、地域医療の一端を担う責任とやりがいを感じながら、忙しい日々の中にも、あたたかな看護を提供できるように努めています。

看護師 H・N
聖母病院の目指す助産師像
たくさんの経験や学びで得た判断力と技術を持ち、自立した助産ケアができること。モニター所見や数値、バースプランに挙げられていることだけでなく、表情やしぐさ、言葉にならない気持ちまでを汲み取りながら先回りして看ていく細やかさを持っているのが聖母の助産師だと思います。敢えて言葉にしなくても自分のことをよく理解し、支えてくれる...そんな安心感と信頼を持っていただけるように日々切磋琢磨するとともに、聖母の助産師像を後輩助産師にも繋いでいきたいと考えています。

助産師 W・M
短時間だからこそ充実したコミュニケーションを
私は「手術室」という非日常的な空間に身を置く患者さんに、安全な看護と安心していただける空間を提供できるように努めています。
患者さんが手術室で過ごす時間は、他部署のように長くありませんので、短い時間でもコミュニケーションを充実させることがとても大切だと思っています。
ケアに必要な患者情報を得る術前術後訪問では、患者さんを良く観察し、患者さんの言葉一つひとつに丁寧に耳を傾け、お気持ちに寄り添えるように心がけています。例えば、赤ちゃんに会える喜びと手術に対する不安が交差している帝王切開術を控えた妊婦さんには、術前から退室までしっかりとお声がけし、赤ちゃん誕生の瞬間を私たちも一緒に喜びあえる幸せな空間となるように、心を込めて援助しています。

看護師 S・N
学会や講師などの経験
私は、2011年から妊産褥婦への食育をテーマとした研究を始め、毎年、母性衛生学会や日本助産学会で発表をしています。聖母病院は分娩件数が多いことに加え、研究に積極的に取り組むスタッフが多いことからも、研究をするフィールドとしても、研究成果を還元する場としても大変充実している環境だと思います。
また、最近では、長年の取り組んできた食育の分野で院外から研修の講師依頼や雑誌の原稿依頼を受けることもあり、責任の大きさと同時にやりがいも感じています。
今後の日本の助産師界の発展には、いかに臨床からリアルな課題を提言できるのかということにかかっていると言っても過言ではありません。それに少しでも貢献できるように自己研鑽し続けていきたいと思います。

助産師 O・S
聖母病院の看護の魅力
私が聖母病院の助産師として働くようになったきっかけは、前職において8年間の看護師経験を積み、在職中に第1子、第2子を出産したことです。
入院し陣痛の苦しみの中で大きな不安に包まれた時、心身ともに些細なことにも敏感になっていた私を救ってくれた助産師の存在の大きさに魅了され、退院後もその感動は続き、「いつか助産師として働きたい」という希望を抱くようになりました。
時が経ち聖母病院で助産師として働きはじめた私は、2年目に第3子を出産し復職してからずっと、家事や育児に協力的な夫や子供たちの助けを受けつつ奮闘する日々です。
同じ志の助産師と「患者さんの立場で考え関わることを大事にする」ための議論を重ね、自分の看護観である「患者さんの足元にいつもいて、かゆいところに手が届くようなケアができる存在でありたい」という思いを大切にしながら仕事を続けられることも、聖母病院の魅力だと思います。
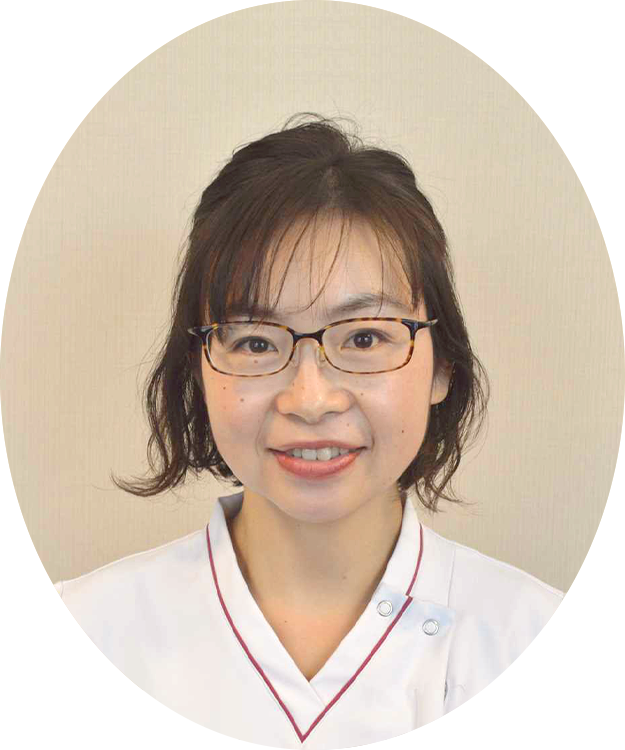
助産師 K・K
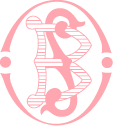 聖母病院 看護部
聖母病院 看護部